㉒相続財産の調査・確定
- 山﨑税理士事務所

- 2022年3月23日
- 読了時間: 5分
更新日:2022年7月13日
相続財産全体の把握は、「相続放棄を行うかどうか」、「どのように財産を分けるか(遺産分割協議)」及び「相続税の申告をしなければならないかどうか」と言った判断をするための基準となります。後から新たな相続財産が発見された場合は、それまで進めてきた手続きのやり直しをすることにもなりかねません。慎重かつ速やかに相続財産の調査を行いましょう。
1. 調査の対象となる相続財産
故人が所有していたプラスの財産とマイナスの財産をすべて把握する必要があります。プラスの財産は、価値があるものをすべてを把握しなければなりません。具体的には、預金、土地、株式、車両、骨董品等が挙げられます。マイナスの財産は借入金や未払金といった負債を言います。
2. 相続財産の探し方
財産調査のヒント
現金 | 金庫、引出、仏壇等の大事なものを保管しそうな場所 |
預金 | 通帳、カード、故人のメール、金融機関のカレンダーや粗品等・残高証明書 |
土地・不動産 | 権利証、登記簿謄本、売買契約書、固定資産税納税通知書、名寄帳 |
その他の資産 | 絵画・宝飾品・その他故人の趣味 |
負債 | 借用書、請求書、預金通帳に借入金返済の記載があるかどうか |
① 遺言書から相続財産を探す
遺言書がある場合には、そこに預金や不動産等の財産目録が記載されてあることがあります。そこから取引があった金融機関の名称や不動産の所在地を把握しましょう。ただし、故人も把握していなかった相続財産が存在することもあります。油断せず下記の手順も省略しないことをお勧めいたします。
② 死亡した方の預貯金の探し方
取引のあった金融機関の支店を特定し、死亡日現在における残高証明書の発行を受ける。
取引のあった金融機関の支店さえ特定できれば、口座番号がわからなくても、その金融機関の支店に対する預金残高の一覧(残高証明書)をもらうことができます。残高証明書は死亡日現在におけるものを取得しましょう。また、残高証明書にはその金融機関に対する預金や借入金のすべてが記載されるので、最近使用されておらず忘れていた預金が見つかることもあります。死亡した方の財産をすべて把握している自信があっても、念のため残高証明書の発行を依頼することをお勧めします。
取引のある金融機関の特定方法は、まずは金融機関から郵便物が届いていないかを確認するといいでしょう。次に故人のメールに金融機関から送られてきたものがないかどうかを確認します。その他にも貸金庫の中に通帳などの手がかりになるものが保管されてあることもあります。
残高証明書の発行は、相続人の中の一人が単独で行うことができます。その場合に必要となる書類は下記の通りです。ただし、金融機関によって若干異なる場合もありますので、事前に電話で必要な書類を確認しておくと良いでしょう。残高証明証の発行には時間がかかることもありますので余裕を持って手続きを済ませましょう。
残高証明書を発行するために必要な書類 |
・被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等 ・発行依頼者が相続人であることがわかる戸籍謄本等 ・発行依頼者の実印及び印鑑証明書 |
③ 預貯金の過去の入出金の内容確認
相続税法上の財産は名義が故人のものに限らない。その財産はそもそも誰が稼いだものなのかが重視される。
残高証明書は相続開始時点での預金残高を把握することができます。しかし、相続財産を確定させるためにはこれだけでは足りません。過去の預金通帳の入出金を確認し、故人が稼いだお金が別の名義の預金になっていないかなどを調査します。ちなみに、なぜこういった調査が必要かと言うと、税務署がこれと全く同じ調査を行うからです。それと、よく税務調査で指摘される点として、死亡直前に引き出した葬式費用の相続財産への算入もれがありますのでご注意ください。
④ 相続する不動産の調査
地番・家屋番号を調べ法務局で登記事項証明書を取得し、不動産の権利関係を確認する。
まず、土地であれば「地番※2」を、建物であれば「家屋番号」を調べます。
「地番」と「家屋番号」は、固定資産税納税通知書や不動産の登記済権利証・登記識別情報通知、購入当時の売買契約書などから把握することができます。また名寄帳を閲覧することで同一市区町村内にある故人所有の不動産を全て確認することができます。
「地番」と「家屋番号」をもとに法務局で登記事項証明書を取得します。登記事項証明書にはその不動産の権利関係が記載してあります。当然故人の所有物だと思っていたものが実は借り物であったり、別の誰かとの共有物であったりする可能性があるため、登記事項証明書は必ず確認する必要があります。
※2「地番」は住所とは異なるので注意が必要です。地番は登記情報の取得や税金など公的に使う土地を表すのに対し、住所は郵便物などを配達する宛先を表します。従来は地番のみ存在したのですが、日本の市街化が進むにつれ、その土地がどこにあるかを地番で特定することが困難になり、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され住所が誕生しました。


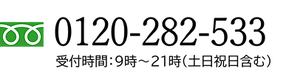
コメント