⑲相続人の調査・確定
- 山﨑税理士事務所

- 2022年3月23日
- 読了時間: 3分
更新日:2022年7月13日
誰が相続人になるかを確定します。後々の手続きで第三者に相続人がもれなく把握できていることを証明するためにも必要になってきます。
まずは法律で定められている「相続人となる者」を理解する必要があります。
次に、その法律で定められた相続人(法定相続人)が誰であるかを証明するための書類(戸籍謄本等)を集めます。
1.法定相続人
相続が発生したときに「相続人になる人(法定相続人)」とその「分配割合」は、法律で原則が定められています※1。この法律で定められた原則的な相続人を法定相続人と言います。
配偶者と子は必ず法定相続人となります。子がいない場合には、直系尊属(父母等)が相続人となります。最後に、子もおらず直系尊属(父母等)もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
※1 実際の分配について遺言等があればそれに従うことになります。その場合でも相続税の計算はこの法律で定められた相続が行われたと仮定して行います。
法定相続人とその相続割合

※第一順位で、子が先に死亡している場合には直系卑属(孫・ひ孫等)が相続人となる。
※第三順位で、兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪が相続人となる。ただし、甥・姪の子供は相続人にはならない。
2.証明のための書類(戸籍謄本等)
故人の預金凍結を解除する場合等にも必要となります。
正確な法定相続人を確認するため、戸籍謄本等を収集する必要があります。戸籍謄本は死亡事項の記載がある戸籍(除籍)謄本だけでなく、故人の出生から死亡までのすべてのものが必要となります。すべての戸籍謄本が必要なのは、戸籍は婚姻、転籍または法改正により新しく作り直されますが、その際に古い情報は新しい戸籍謄本に記載されないためです。
戸籍の取得方法
申請できる人 | 本人・配偶者・直系尊属・代理人(委任状が必要)など |
取得できる窓口 | 本籍があった市区町村役場(郵送可) |
必要なもの (市区町村により異なる場合があります。) | ・発行手数料 ・身分証明書 ・郵便の場合は定額小為替と返信用封筒(切手) ・代理の場合は委任状 など |
具体的な戸籍謄本の集め方
①まずはご自身の戸籍謄本を取得します。
これにより、ご自身が故人とどのような関係であったかを証明することができます。
↓
②故人の戸籍謄本を集めます。
この際、①で取得したご自身の戸籍謄本が必要になります。
故人の本籍地の窓口で「相続があったので、出生から死亡までの戸籍を取れるだけください。」と伝えましょう。
↓
③多くの場合は本籍地で取得できる戸籍だけでは足りません。
②の際、実際に戸籍謄本が出てきたら、窓口の担当の方に「次はどの戸籍を取ればいいですか?」と尋ねてみましょう。
戸籍謄本が足りない場合は次にどこの役所に戸籍謄本を請求すればいいかを教えてくれます。
↓
④あとは出生にたどり着くまで戸籍謄本の請求を続けます。
この際、遠方の市町村に過去の戸籍がある時は、郵送により戸籍謄本の請求を行いましょう。
請求方法は市町村ごとに異なりますので、まずは電話で問い合わせてみるのが良いでしょう。
ただし、郵送で請求した場合には、次にどこの市役所に請求すべきかを自分で判断しなければなりません。古い戸籍などは一般の人が読み解くのは難しいと思います。
戸籍については司法書士に相談すると良いでしょう。


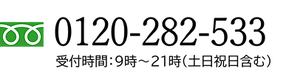
コメント